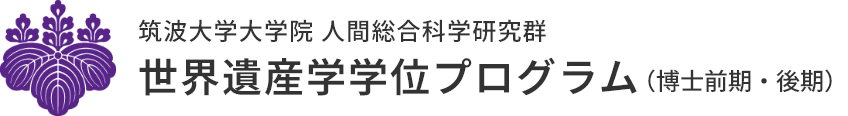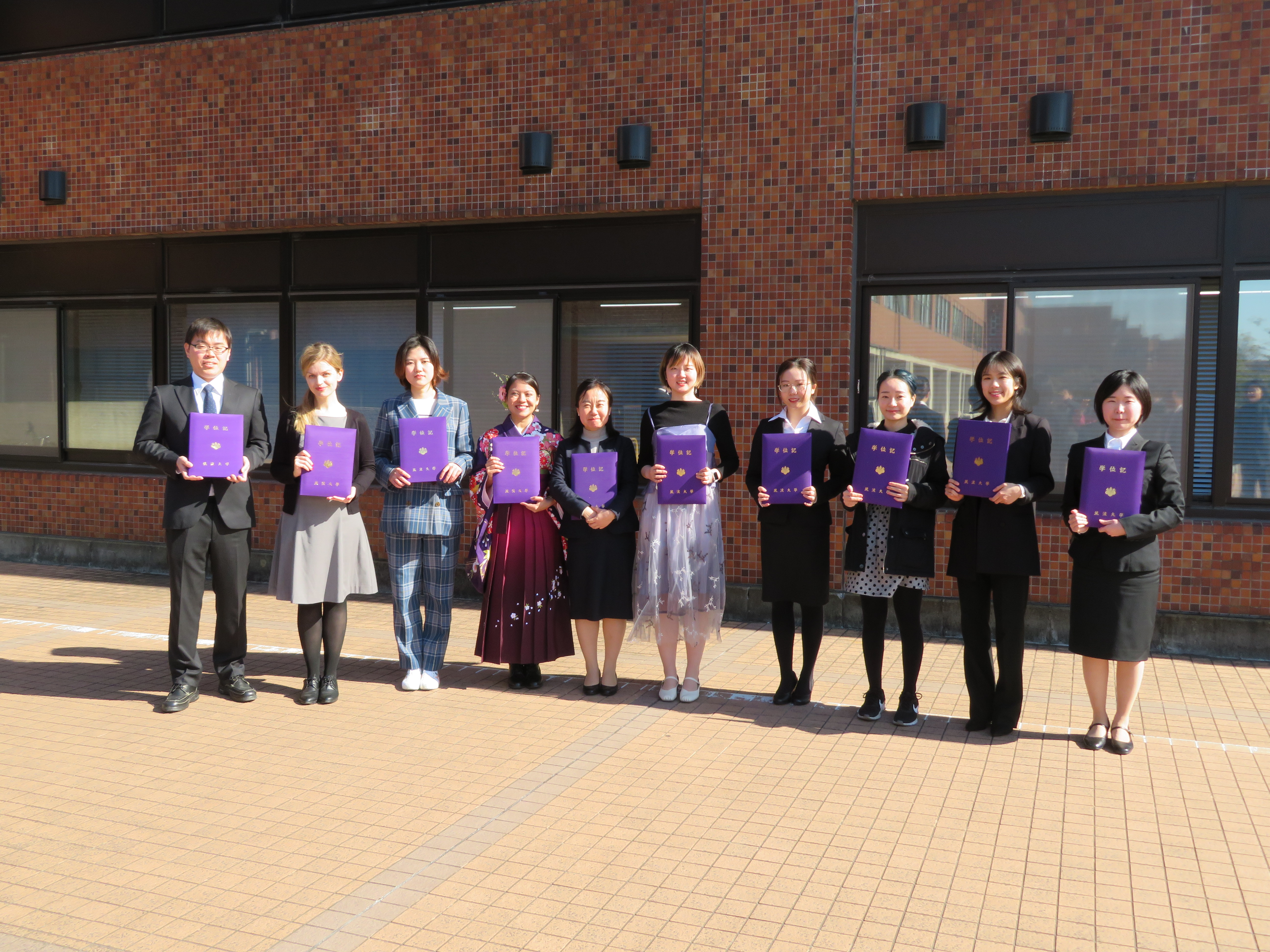
修了生の声
Voice of Graduates
学生による学位プログラム紹介動画
Introduction Movies by Students
修了生が在学中の思い出を動画にまとめ,学位プログラムの魅力をつたえてくれてます♪
2015年度修了生が2年間の思い出をまとめてくれました!!どうぞ、御覧ください。
博士前期課程修了生
Graduates of the Master’s Program
 于 濰赫 YU WEIHE
于 濰赫 YU WEIHE
2022年度修了 日本の金融機関の中国現地法人 営業
日系企業の現地法人を主な顧客として、顧客のニーズを理解し、金融ソリューションやサービスを提案します。例えば、貸付や預金、手形、両替、信用状などが挙げられます。
大学時代は様々な演習や調査を参加することができました。山形の寺院の絵馬の材質調査、白川郷の合掌建築の見学、白馬村のバーの音楽空間の調査、龍ヶ崎市の牛久沼の住民に対するインタビューに基づく論文の執筆、生涯学習センターの地域住民へ研究の内容発表などです。それによってフィールドワークの能力やコミュニケーションの能力を高めて、自分の研究にも役に立ちました。
また、院生としての2年間を通じて「どのような細かいことでも真剣にやる」という習慣を身につけました。以上を踏まえて、在学中に積み重ねた知識をアウトプットし、池田真利子先生のご指導のもと、専攻優秀論文賞や江崎賞を受賞することができました。
世界遺産専攻にはいろいろな研究分野の先生がいらっしゃいますし、先生の方々もすごく親切です。また、海外留学、国際学会発表、国際組織でのインターンシップの機会も豊富です。世界遺産学学位プログラムに入学すれば、絶対楽しい研究の世界を垣間見ることができると思います。

FAIRUZ Alfira ファイルズ・アルフィラ
2022年度修了 まちづくり・文化財コンサルタント
学部の時代から、建築遺産について興味を持っています。建築設計の視点だけでなく、他の分野からも遺産について広く学びたかったため、世界遺産学の修士課程に進学しました。1年生の間には、さまざまな授業と演習を受け、多くの国内の文化遺産を訪れました。2年生はほとんど研究で、インドネシアの民族を研究し、年度休み等はインドネシアに行きました。その他、余裕のある時間を利用し、古民家を再活用する設計を行う建築事務所で長期インターンシップをしました。そのおかげで、建築遺産の調査のやり方などを詳しく学び、研究にも活かせ、最優秀論文賞まで頂きました。
現在は建築遺産だけではなく、国内の全体的な文化財を携わっている仕事をやっております。市町村からの業務がほとんどであり、文化財保存活用地域計画や史跡の整備基本計画などを作成したり、住民とのワークショップの参加や支援をしたり、文化財保存活用の委員会に出席したりしております。大学で学んだ文化財に関する行政の体制、補助金の申請などに実際に関わっており、専門家になるために必要な経験だと思います。
世界遺産学では遺産に関する好奇心を満たすことができ、母国とはまったく異なる文化などを楽しみながら深く学ぶ機会でした。世界遺産や文化遺産に関する知識を追求したいのであれば、このプログラムは最適なプログラムのひとつだと思います。私もいつかまた戻りたいですが...。

神田麻衣子 Maiko Kanda
2020年度修了 公益財団法人広島平和文化センター 広島平和記念資料館 学芸員
私は、当時の勤務先での戦争遺跡撤去の動きに疑問を感じ、文化財としての価値づけと保存活用について研究したいと思い、2018年度に入学しました。
40代での挑戦でしたが、長期履修制度とオンデマンド授業や土日開講科目を利用して、行政職の公務員を続けながら博士前期課程を修了することができました。
研究に行き詰まった時は、ゼミメンバーから率直な意見を貰うと不思議と先が見通せるようになり、多様な国籍、年代、研究分野の学生と学び合えたことが一番の糧となりました。
在学中にボランティアで「鹿島海軍航空隊跡地基礎調査報告書」の執筆に関わったことや、修了後に日本造園学会全国大会で修論研究を発表したことも貴重な経験でした。
以前から戦争関連博物館の学芸員になりたかったのですが、出身学部は美術系で、経験もなく年齢的にも半ば諦めていました。ところが、修了した2年後に広島市の外郭団体に転職することができ、今は学芸員として働いています。
担当業務は被爆者証言ビデオの制作、常設展示の更新、附属施設の展示計画や資料収集などで、中でも被爆建物を活用した展示計画は修論研究と通じる内容でやりがいがあります。
残りの職業人生はあまり長くありませんが、世界遺産学学位プログラムに入学したことで開けた学芸員の道を邁進していきたいと思います。
人生、何が起こるかわかりません。
社会人の皆さん、学びたい気持ちを大切に、一歩踏み出してみませんか。

胡皓然 Hu Haoran
2020年度修了 筑波大学世界遺産学学位プログラム 博士後期課程3年
私は2017年10月に筑波大学世界遺産専攻(現博士前期課程世界遺産学学位プログラム)に研究生として入学しました。2019年4月には博士前期課程に進学し、2021年3月に同課程を修了しています。研究生・博士前期課程の5年間に、中国北魏時代の仏教美術に関する研究を特定テーマとして取り組んできました。修士学位を取得した後に、自分の研究をより深く進めるため、2021年4月に世界遺産学学位プログラム博士後期課程に進学し、現在は博士後期課程3年生です。
本専攻について一番面白いことは、多様な研究領域に関する授業です。それは私の学部の授業(中国の大学)とは全く異なっていました。自分の専門分野に直接関連する授業以外に、最も興味を持ったいくつかの授業は、佐伯いく代先生の「生物多様性」、黒田乃生先生の「文化的景観」、下田一太先生の「建築遺産論」です。これらの授業は私の研究とは直接関係がありませんが、異なる専門分野を広く学ぶ視野を育ててくれました。私の研究は北魏時代の仏教石窟に焦点を当てていますが、現在研究を進める際、石窟と建築の関係や当時の人々が石窟の位置をどのように選んだのか、宗教建築(石窟)と自然環境を調和させる方法について頻繁に考えます。これらは修士課程での収穫であり、異なる専門分野を統合的に議論することができるこの経験は、筑波大学の世界遺産学学位プログラムでの最も印象深いことの一つです。

田代江太郎 Kotaro Tashiro
2019年度修了 上毛新聞社 出版編集部
群馬県の地方新聞社、上毛新聞社で働いています。現在は出版編集部という部署で、書籍編集やさまざまな記事の取材・執筆などの業務を担当しています。観光やまちづくりに興味があり、在学中は伊藤弘先生のゼミに所属していました。修士論文では栃木県日光市を対象に、世界遺産「日光の社寺」やその門前町を含めた観光のあり方を研究しました。
普段の業務内容と在学中に学んだことは、直接的には関係がないように思われるかもしれませんが、どちらも対象について深く知り理解しなければならない点が共通すると思っています。記者として出来事や人物を取材するときは、下調べをしてから実際に取材をして、出来事の経緯や人の行動、思いを理解しなければそれらをしっかりと伝えることはできません。観光のあり方を考えるときも、実際に足を運んで土地の魅力や観光の現状を知る必要があると思います。
世界遺産専攻では座学だけではなく実習もたくさんあり、実践的な学びを得られました。特に印象に残っているのは、白川郷に滞在する演習です。合掌造りの宿に泊まり、地域の方々と一緒に農作業をしたり、昔の生活についてお年寄りにお話しを聞いたり、伝統芸能を見せていただいたり…。白川郷のことをより深く知り、遺産としての価値がどこにあって、どう守り伝えていくのかを考えた経験は、現在の仕事にもつながっていると思います。

久我昌江 Masae Kuga
2019年度修了 国立科学博物館
在学前は美術作品を製作していたこともあり、文化財を取り巻く環境に興味を持っていたため、この専攻に進学を希望しました。在学中は演習が非常に多く、得た情報をアウトプットすることに苦労した覚えがありますが、先生や同期、研究室の方たちのお陰で、楽しく充実していた思い出があります。修士論文では、図書館に収蔵された木質保存箱の劣化状態に関する調査をしましたが、研究室では論文のテーマに限らず、多種多様なテーマに関わる機会をいただけました。現在は、国立科学博物館でボランティアさんに対応する部署に所属しています。仕事内容は、ボランティアさんが展示をお客様にご案内されたり、職員が作ったプログラムを実施されたり、そういったボランティアさんの活動を支援することです。在学中に博物館でインターンシップができた経験が、仕事への姿勢の地盤になっていると思います。この専攻では、多くの方の助力を得ることができたことはもちろん、大小伴わず様々なことに挑戦する環境を提供していただけました。

井上葵 Aoi Inoue
2015年度修了 公益社団法人日本ユネスコ協会連盟
世界遺産にはもちろん興味はありましたが、ユネスコを研究のテーマにしていたため、特定の遺産や分野に絞ることなく、幅広く様々な授業を取りました。そのため1年生の夏休みは演習ばかりになり、家にいる時間が無くなる程、様々な場所に行きました。また、環境問題にも興味があったので、自然保護寄付講座の授業を生命環境科学の生徒と一緒にとっていました。世界遺産を通して、物事を多角的に見ることを学び、違う価値観を持つ人々と議論した経験は仕事に活かされています。
現在は公益社団法人日本ユネスコ協会連盟というNGOで働いています。UNESCO憲章に賛同し、平和を目指す団体です。業務は教育を中心に多岐に渡り、東日本大震災で経済的に困窮している生徒を支援する奨学金の事務局から教員向けの研修会の開催、小学校での出前授業、日中韓の高校生を集めた交流会の運営など様々です。最近ではSDGsに関係する業務が増えてきました。SDGsとは多くの企業や行政も取り組んでいる「持続可能な開発目標」という国連が発表した、世界中の人々が取り組まないといけない目標です。
学位プログラムには世界遺産の名の元に様々なバックグラウンドや興味を持つ生徒、先生が集まっています。自分の研究を深められることはもちろん、今まで知らなかった分野の話を聞き、視野を広げ、新たな考え方を得ることができます。

菅澤由希 Yuki Sugasawa
2014年度修了 千葉県教育庁教育振興部文化財課 文化財主事
私は学部で考古学を学びましたが、より広い視野を持って文化財の保護や活用の仕組みを学びたいと思い、進学しました。
在学中は、様々な場所に演習に行ってたくさんフィールドワークをしたことが印象に残っています。海外の世界遺産の現場も訪れ、文化財保護の最前線を目の当たりにすることができました。自身の研究では、指導教員の先生にご指導いただきながら、世界遺産登録を目指す遺跡の保護を見据えた考古学的調査を行いました。自分が調査に携わった遺跡が世界遺産に登録されたときは、感動しました。
現在は、千葉県の埋蔵文化財専門職員として、発掘調査や、文化財の指定や登録に関する業務、文化財保存活用地域計画に関する業務などに携わっています。千葉県の歴史や文化を守り後世に伝えていくため、日々奮闘しています。
現在の業務では、学生の時に見学に行った重要文化財のお寺や伝統的建造物群保存地区に、県の担当者として関わることになることもあり、とてもやりがいを感じます。また学生時代は、多様な意見を持った友人たちと共に過ごしましたが、この経験があるからこそ、仕事にも柔軟に粘り強く取り組める力が付いたのではないかと思っています。
世界遺産学学位プログラムは、様々なことにチャレンジできる環境だと思います。入学後は思い切って色々な環境に飛び込んでいってみてください。
博士後期課程修了生
Graduates of the Doctoral Program

周怡杉 Zhou Yishan
2019年度修了 中国文化遺産研究院 石窟寺院石刻(岩土)文化財保存修復研究所 館員
文化遺産の素晴らしさはどのように後世へ伝えるのか。この課題について微力でも尽くしたいので保存科学を勉強し始めました。しかし文化遺産を守る事業は一つの学問で成立できるわけではありません。
世界遺産学学位プログラムでは遺産の「有形的な存在」を守る研究に限らず、遺産の「無形的な価値」を世の中に語ることに関わるさまざまな分野と触れ合えます。ここはバックグラウンドや研究領域が異なる生徒や先生と学際的な交流が自由にできる場です。学位プログラムで得られた出会いのおかけで、他分野の視点から自分の研究を常に再確認すべきだと意識できました。それは現在私の中国文化遺産研究院での仕事と繋がっています。
中国文化遺産研究院は中国国家文物局に所属する文化遺産保存に関わる専門研究機構です。入職後は石窟寺院、石刻文化財の保存に関する科学調査や研究を主に担当しています。実務では、各種多様な遺産を対象にして科学問題の解決を突き詰めることと共に、保存修復作業手法や日常的な維持管理対策も配慮しないといけません。多角的な視点、柔軟的な頭脳、「生涯学習」の姿勢は学位プログラムで得られた一番貴重な収穫だと思います。

Helga Janse ヤンセ・ヘルガ
2019年度修了 National Museums of World Culture in Sweden Curator
I am working as a Curator at the National Museums of World Culture in Sweden, where I specialize in Asian cultural heritage. In the role as Curator, I have the pleasure of engaging in a range of different projects, involving both exhibitions, collections, and research. It is great fun, and I am especially happy and grateful to realize how useful my experiences from the University of Tsukuba’s World Heritage Studies Degree Program are in my work.
I obtained my PhD from the University of Tsukuba in 2020 and have very fond memories from the World Heritage Studies Degree Program. Especially memorable were the engaging discussions and exciting excursions.
The teachers were excellent in how they helped me to grow, for example by offering me opportunities to teach and hold lectures, thereby helping me to gain relevant experience. Even after graduating, the teachers have continued to support me in various steps in along the way, for example in acting as reference persons when applying for research grants or work. I really hope to continue working together in various projects moving forward.

伊藤文彦 Fumihiko Ito
2018年度修了 三重県環境生活部文化振興課/三重県教育委員会社会教育・文化財保護課
文化財保護技師
私は現在、三重県庁で文化財保護専門職員として勤務しています。元々、入学前から三重県の文化財保護に従事していたのですが、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の保護に携わる中で、自身の専門性のみでは文化遺産の保護を十分にできないと感じ、大学での学びを決意しました。
働きながら通学しましたので、十分な学びの時間を確保するのに苦労しましたが、それでも、修士2年、博士3年の在学期間中、様々な講義・演習を通して、それまで文化遺産保護の現場で感じていた様々な疑問が、実に鮮やかに整理されていくことに驚く日々を過ごしました。同級生や先輩、後輩との議論も活発で、それにより、理解が一層深まったことも多くありました。さらに、在学中に世界遺産委員会や紀伊半島での国際的な研修会に参加させて頂いたことは、私の中で大きな経験となり、その後、私自身が国際的な活動に参加していくことの動機ともなりました。
私は現在も三重県で文化財保護に従事しており、大学での学びがそのまま日々の業務に繋がっていることを実感しています。また、研究活動を継続しつつ、地元の大学で世界遺産論を講じているほか、イコモス文化の道国際科学委員会での国際的な議論にも参加しています。
筑波大学大学院世界遺産学位プログラムは、我々、文化財専門職員が悩み苦しむ時に、それを解決していく考え方を学べる大学院であると思います。学びなおしを考える方々にも強くお勧めしたいです。

李 雪 Xue Li
2017年度修了 秋田県立大学建築環境システム学科 助教
私は中国の大学の建築学科を卒業し、留学生として日本にやってきました。修士時代は他大学の大学院博士前期課程で近代都市史に関する研究を行いました。そこで、「過去」に関する研究にとどまらず、「過去」が現在に及ぼす影響や、将来への「過去」の遺産の価値についても興味を持ち、本プログラムの博士後期課程に進学しました。博士論文は無形文化遺産に指定されている木造技術を用いて建設する中国の少数民族の木造民家の建設過程に関する研究を行いました。
博士後期課程では、セミナー以外に授業がないため、最も印象深い経験は地域に密着したゼミナール活動でした。黒田先生が指導する文化的景観研究室では、さまざまな地域でのゼミ活動が行われています。私が所属していた期間に、世界遺産である石見銀山の大森町で「石見銀山ゴブリン展」の準備と企画に参加しました。
地元の子供たちやお年寄りと一緒にゴブリンを作成し、国際ワークキャンプの若者たちと共に石見銀山の町並みの魅力を発見し、写真や映像を撮影しました。大森町に2週間滞在しながら、地域の文化を理解するために地域に溶け込むことの重要性を痛感しました。今もなお、地域に滞在し、地元住民と訪れる人々との交流を大切に考えています。
現在、秋田県立大学で建築の基礎知識を教えながら、地域の特徴を持つ小屋の建設プロセス、集落の景観形成、地域資源としての近代街並みの形成、空き家・空き施設の活用に関する研究を行っています。これらはすべて地域に関連する研究テーマであり、世界文化遺産学の専攻で培った地域との関わり方を最大限に活用しながら、研究活動を楽しんでいます。

河﨑衣美 Emi Kawasaki
2013年度修了 奈良県立橿原考古学研究所
私はこの世界遺産学学位プログラムで文化遺産の保存科学に関して研究し、博士前期課程と後期課程を修了しました。私の学位論文のテーマは煉瓦や石材の保存に関することで、材料科学的な視点から文化遺産の保存を考えることでした。保存科学の研究はともすればミクロの世界に没入してしまう可能性もありますが、演習やその他のフィールドワークにおいて様々な文化遺産の保護活用の現場を体験する機会に恵まれ、専門性を突き詰めながら学際的な視点を持って研究することを学びました。
現在は奈良県の保存科学担当者として、主に埋蔵文化財の保存処理や保管管理、附属博物館の展示環境管理等を行うと同時に、保存科学に関する研究を継続しています。特に保存処理においては、木製品や金属製品、遺構の保存など、素材や規模、時代や保存体制も様々なモノを対象としており、在学中に広い視野を持って学べたことが現在の業務に活きていると感じています。
現在の職に就いて改めて思うことは、文化遺産の保存には柔軟な思考が求められるということです。世界遺産学学位プログラムは多彩な専門性を持つ先生方と学友達からの多角的な刺激を受けられ、柔軟な思考を育てる掛け替えのない場であったと感じます。