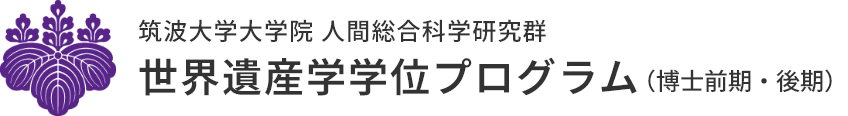「遺産整備計画演習」報告
2025年度の遺産整備計画演習では、関東地方の遺跡や街並みなどの文化遺産について、その保存と活用の実例を知るために4回の見学に赴きました。
初回の見学は茨城県土浦市にある土浦城とその城下町で行われました。われわれ学生は事前課題として作成していた、現代の地図に江戸時代の町割を重ね合わせたものを持参し、かつての城下町の痕跡が現代都市としての土浦のどこに、どのように残されているかを見て学びました(写真1)。土浦ではかつて町並み保存が検討されるほど伝統的な建造物が存在していたといいますが、現在ではわずかに蔵造りの商家が残るのみです。それでも、確かに残されている屈曲した街道や、堀の跡、看板建築などを発見し、そこから昔の街の姿を読み取る方法を学ぶことができました。
2回目は茨城県内の筑波山麓の史跡と建築を巡る行程でした。
はじめに小田城跡を訪れました。小田城は中世に地域の中心的な存在だった城郭で、土塁や庭園の復元、建造物の平面表示などの整備が行われています。筑波鉄道の廃線跡である自転車道との取り合わせも興味深いものでした。次に訪れたのは平沢官衙遺跡で、古代の倉庫が3棟復元されています。意図的に3種類の異なる様式の倉庫が並び立つように復元した当時の行政の判断は、遺産整備を考える上での好例ではないでしょうか(写真2)。最後に旧矢中家住宅を訪れ、近代建築が市民の手によって主体的に保存活用される様子を見ることができました。この建物に惹かれ、ボランティアガイドになった方の語りも印象的でした。

写真1 事前課題として作成した土浦城下町の重ね合わせ地図

写真2 平沢官衙遺跡の復元倉
3回目は埼玉県川越市の街並みを訪問しました。川越市幸町とその周辺の一区画は、江戸時代初期の町割の上に、明治時代から戦前期までの伝統的な建造物が立ち並ぶ町並みとして、重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。この見学ではこれらの建造物に加えて、酒蔵を転用した観光客向けの複合施設である小江戸蔵里や、織物市場を転用したインキュベーション施設のコエトコなど、保存地区外の建造物も多く見学し、そうした区域における歴史的建造物の活用が持つ可能性について考えました(写真3)。また保存地区内ではジェントリフィケーションに代表される現代的課題について説明を受け、保存地区の設定がゴールではないことをあらためて確認しました。
4回目は千葉県香取市の佐原において、小野川と佐原の町並みを考える会による市民主導の町並み保存の歴史を学びました。まず説明を受けたのち、重要伝統的建造物群保存地区を歩き、小野川を核として形成された町並みを自らの目で見ることで、同じく小野川を核として展開した保存運動に思いを馳せました(写真4)。伝統的建造物の保存について考えるときには、こうした周辺環境や町並み成立の要因などに目を向けることもやはり重要なのだと実感しました。
本演習では、近代の町並み保存が積極的に進められた地域とそうでない地域、古代や中世の遺跡など、さまざまな性格の遺産について、遺産整備の視点から比較して学びました。特に、遺産に訪問した際にどこをどのように見るべきか、というものの見方や、整備や保存活動を行う側の視点に触れたことは、今後の研究においても非常に参考になるものでした。

写真3 織物市場の転用により生まれたコエトコ

写真4 佐原の町並みを流れる小野川
(M1 松浦)